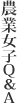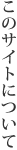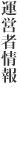食べ方、それは「キャスティング」のようなもの
珍しい野菜を作る新規就農者は多いが、自らを「日本一レアな野菜セット農家」と称し、加熱向きの根菜・花芽類を中心に、ひときわ珍しい野菜作りに取り組むのがzund耕園(ずんどこうえん)の小野原亨(とおる)さん・あやさん夫妻だ。2015年に新規就農し、高島市の泰山寺地区に45aの土地を借りて耕作している。
その野菜がどのくらい変わっているかというと、カルドン、サルシフィ、パースニップ、ビーツ、フェンネル、セロリアック、ルートパセリなど。これらの名前を聞いて、その姿形や食べ方などにピンとくる人が一体どのくらいいるだろう。
「おいしいからこそ、人々の手で受け継がれてきた固定種・在来種。そのなかでも、私たちが本当においしくてワクワクするものを取捨選択してきました」という、あやさん。就農してからの5年間を「実験期間」と定め、育て方や、見せ方、食べ方を試行錯誤してきた。日本では主に北海道などの寒冷地で育てられるセロリアックも、今では500グラム以上のサイズにまで育てられるようになったという。
これまで、あまり商品価値を見出されてこなかった間引き菜や花芽も、積極的に商品化してきた。
「作物の成長過程を味わうことが、私たちのコンセプトにフィットしていると感じるんです。うちの野菜は変わっているし、安くもない。けれど、やっぱり食卓という舞台でキラキラ輝いてほしいんです。『こんな料理に合いますよ』と提案することで生まれるニーズもあります。これって野菜に役を振っているとも言えますね」と、既成概念にとらわれない農業を楽しんでいる。


おいしさにこだわり、肥料は植物性のみ。農薬も使わない
肥料は地域から出る、米ぬか・もみ殻・木灰などの植物性素材を利用している。
「初年度、鶏糞を入れたら生育過剰になり、おばけみたいな野菜が出来てしまったんです。その後2年ほど無肥料栽培にしたところ、生育は遅くなりましたが、特にビーツの味が劇的においしくなりました。ここは、黒ぼく土壌のホクホクの土。今のところ少しの植物性肥料でおいしく育つ野菜がほとんどです」と、おいしさへのこだわりを見せる。
農薬も安全性への配慮から使わず、土を太陽熱養生処理したり、野菜を混植したりして、病害虫や雑草から作物を守っており、高島市農産ブランドの認定を受けている。

大切なのは、お客様とのコミュニケーション
こうして育てられた野菜は、地域の道の駅でも売られる。初めは珍しすぎて売れなかった野菜も、ラベルやPOPを工夫し、少量サイズにするなどして地道に販売を続けたところ、顧客が定着してきた。
コロナ禍以降は、通販サイトポケットマルシェからの注文も増えた。ポケットマルシェは、消費者が全国の農家や漁師と直接やり取りしながら食材を購入できるのが特徴だ。消費者との関係構築に力を入れてきたあやさんは、
「コロナ禍の外出自粛期間を経て、人との繋がりがいかに大切かということが浮き彫りになりました。お客様との文通のようなコミュニケーションに費やしてきた時間も肯定されたようで嬉しいです」と語る。

夫婦だからこそ、必要と思えるJGAP認証制度
「問題点の指摘が、夫婦だとつい感情的になり脱線してしまいます。折り合いをつける意味でも信頼のおけるガイドラインが必要だと思いました」という、あやさん。2020年4月にJGAPを取得した。
JGAP(Japan Good Agricultural Practice)とは、直訳すると「日本の良い農業のやり方」。栽培・収穫・農産物取り扱いの3つの工程において、食品安全・環境保全・作業者の安全・農場管理・人権福祉を守るための基準が設けられており、農林水産省も推奨している認証制度だ。
2020年の時点でJGAPを導入した農場は、全国で2,000軒あまり。約6万軒で導入されている家族経営協定に比べると少ないが、家族経営協定が家族間の話し合いに基づくのに対して、JGAPは協会が定めた基準が前述のように細部にわたって設定されており、審査が毎年行われるため、状況を客観的に改善できるというメリットがある。
自らの強みを「非農家出身ゆえの独自性」と分析する、あやさん。今後は、ビーツの加工品づくりや食育などの6次産業化にも積極的に取り組み、雇用を生み出すことで地域に貢献したいと考えている。アートで磨いてきた感性を生かし、これからも「ズンズンズンドコ♪」と進んでゆく。