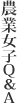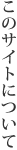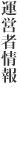自然大好きな少女が野菜農家になるまで
近江八幡市大中(だいなか)町。ここは、かつて四十数か所あった琵琶湖の内湖のうち、最も大きな大中湖が干拓された土地だ。昭和30年代に近代農業のモデル地域として整備され、全国から216戸が米農家として入植した。しかし、昭和45年からの減反政策により、やがて米農家は野菜農家や畜産農家へと変わっていった。
びわこだいなか愛菜館(以下、愛菜館)が大中町にできたのは平成10年のこと。湖岸道路の敷設を機に、6戸の農家が出資して建てた直売所だ。新鮮な野菜が毎日並び、利用客で賑わう。
その愛菜館に野菜を納める農家の一人が、小林ファームの小林めぐみさんだ。サラリーマンの家庭に生まれ育ったが、自然や動物が好きで農家の友達がうらやましかったというめぐみさんは、大学でアニマルウェルフェアを学び、結婚を機に滋賀に移り住むと、夫の家業だった近江牛の肥育の手伝いや家庭菜園をするようになっていった。
そんなある日、愛菜館の出資者の一人だった義父から、間もなく完成する予定の愛菜館を手伝うように求められた。話し合いの末、めぐみさんは牛の肥育の片手間にできそうな野菜栽培ならできると考え、野菜を愛菜館に出荷することになった。そして、かねてから農薬の危険性を懸念していためぐみさんは、農薬や化学肥料を使用しないことを条件に、野菜農家としての一歩を踏み出した。

評価されない時期を経てたどり着いた、開き直り
出荷のために畑の面積を広げためぐみさん。家庭菜園でも長らく農薬を使用していなかったことから、農薬・化学肥料不使用で野菜を育てることはさほど難しくなかった。ところが、収量が少ないぶん商品の価格は上げざるを得ず、思うように売れないという状況に直面した。しかも、牛の肥育の合間に畑の管理をすることは、思いのほか難しかった。
自分の考えが甘かったということに気づいためぐみさんだったが、採算や効率重視の農業へと、すぐに方向転換できるほど器用でもなかった。なかなか理解してもらえないもどかしさと、顧客の言い値で販売するというモヤモヤを抱えたまま、10年ほど過ごした。しかし、
「あるとき、理解してもらいたいなんておこがましいと、ふっきれたんです。私は、自分が農薬を使いたくないという、ただそれだけ。人から「偉いね」と褒めてもらいたくて農薬不使用を貫いているわけじゃない。ほかの農家さんだって、好んで農薬をまいているわけではないと思うから、私は自分がしたいことをできれば、それで幸せだと思うようになりました」。

畑は、まるで宝探し
7月、めぐみさんの畑には草が生い茂り、野菜を探すにも一苦労だ。しかし、めぐみさんの案内で畑を探索すると、スイカ・オカワカメ・オクラなどの野菜が確かにある。まるで宝探しのようだ。
農業と育児の両立が難しく、草刈りが間に合わずに放置したところ、自分の畑の野菜は雑草に負けないことが徐々にわかってきたという。そして、ある日、ジャングルのようになった雑草を一気に刈ったところ、翌日には大量の虫が野菜に付くのを目の当たりにして、「無駄な除草はしなくて良い」と確信した。
特に、キャベツ・白菜・ブロッコリーは、オオイヌノフグリ・ホトケノザ・ハコベなどが病害虫から作物を守るため、本当にきれいなものが採れる。野菜によっては必要に応じて除草することもあるが、一気に刈り取ってしまわないように気を付けているという。化学肥料を与えずゆっくり育っためぐみさんの野菜は、病気にも負けない。

農業で世界が広がった。農家という生き方
元来は人見知りだというめぐみさんだが、自分で育てた野菜を販売するようになって、人とのコミュニケーションが楽しくなり世界が広がったという。初心を貫いたからこそ出会えた仲間の存在も、気持ちが折れそうなときには心の支えになった。何より、大好きな自然のなかで仕事をすることができ、好きなものを食べられる野菜農家の仕事が気に入っている。めぐみさんにとって農業とは、生きるための糧というだけでなく、自身の人生を表現するうえで必要な「生き方」そのもののようだ。
「私は嘘をつけない性格。こんなことをしたら地球環境に悪いとか、こんなものを食べたら体に悪い、と思いながら我慢するのではなく、せっかくの人生なんだから、気持ちの良い選択をしていきたい」。
近年はSNSでの発信に加え、イベントなどで対面販売する機会も増えたため、「小林ファーム=農薬・化学肥料不使用」という認識が消費者に浸透してきた。ビーガンなどの食に関心の高い人からの人気も根強く、めぐみさんのモヤモヤもようやく晴れそうだ。